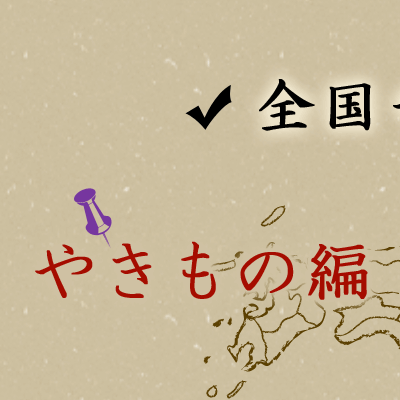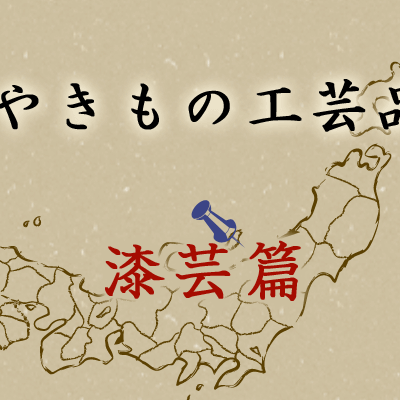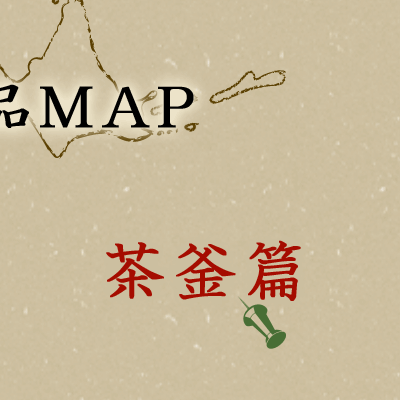金彩(きんだみ)の貝合せ
 貝合せは元々、平安時代に物合わせの一種として様々な貝の珍しさや美しさを競う遊びでしたが、平安末期になると、2つに分けた貝の対を見つける、カルタのような遊びに変化しました。
貝合せは元々、平安時代に物合わせの一種として様々な貝の珍しさや美しさを競う遊びでしたが、平安末期になると、2つに分けた貝の対を見つける、カルタのような遊びに変化しました。
やがて貝の内側には同種の絵や、和歌の上の句と下の句を描くようになり、江戸時代には内側に金箔や金泥などの金彩(きんだみ:金箔 や金泥でいろどること)の細工を施すようになりました。
また、「貝桶(かいおけ)」と呼ばれる貝を入れる2つ1組の桶に入れた貝合せの道具一式は、後に嫁入り道具の一つとされ、現在では雛道具の一つとなっています。
鳳笙(ほうしょう)
 笙(しょう)は雅楽などで使われる管楽器です。外観が羽を休めた鳳凰(ほうおう)の姿に似ていることから、鳳笙(ほうしょう)という美称で呼ばれ、その美しい姿に見合う美しい音色は、「天の声」にも例えられています。
笙(しょう)は雅楽などで使われる管楽器です。外観が羽を休めた鳳凰(ほうおう)の姿に似ていることから、鳳笙(ほうしょう)という美称で呼ばれ、その美しい姿に見合う美しい音色は、「天の声」にも例えられています。
写真の鳳笙は煤竹の素材に、本金蒔絵で桐葉文と純銀の金具が施されています。
笙は高さの異なる音を一度に鳴らすことができ、指孔を5~6つ同時に押さえて、和音を響かせる「合竹(あいたけ)」という奏法が特徴です。
尺八
 フルートやリコーダーなどのエアリード楽器に分類される尺八(しゃくはち)は、奈良時代に雅楽の楽器として中国より伝来しました。
材質は主に真竹の七節(根に近い部分)から作られ、標準の長さが一尺八寸であるところから尺八と呼ばれています。
フルートやリコーダーなどのエアリード楽器に分類される尺八(しゃくはち)は、奈良時代に雅楽の楽器として中国より伝来しました。
材質は主に真竹の七節(根に近い部分)から作られ、標準の長さが一尺八寸であるところから尺八と呼ばれています。
尺八というと、僧が籠などの被り物をして吹いているイメージを持つ人もいるでしょう。
これは虚無僧(こむそう)のことで、室町時代に現れ、江戸時代には幕府公認になりました。
彼らは普化宗(ふけしゅう)という禅宗の一派を作り、尺八は法器として用いられます。
その尺八は普化尺八と呼ばれ、現在の尺八の元になりました。
後に琴古流や都山流といった流派も誕生しました。
扇子
 扇子(せんす)と聞くと、暑い夏などに仰いで涼しい風を起こす道具というイメージの人が多いのではないでしょうか。実はさまざまな使い道があり、日本舞踊や芸妓・舞妓が舞う時、落語家がお箸や盆などを表す際に扇子を用います。
扇子(せんす)と聞くと、暑い夏などに仰いで涼しい風を起こす道具というイメージの人が多いのではないでしょうか。実はさまざまな使い道があり、日本舞踊や芸妓・舞妓が舞う時、落語家がお箸や盆などを表す際に扇子を用います。
京都には京扇子と呼ばれる扇子もあります。歴史は古く平安時代、源氏物語にも登場している扇子。無限に広がる「末広がり」の形をし、縁起が良いという意味合いもありますが、 現代までの長きに渡り人々に愛されている「縁」というのも感じますね。
京扇子:仕立てや資材などが京都・滋賀を中心とした国内生産で、京都の扇子組合に加入している扇子のこと
鼓・和楽器
 ポン、ポンと音色が響く楽器、鼓(つづみ)。歌舞伎や能などのお囃子で用いられる和楽器です。写真の鼓は小鼓(こづつみ)といい、左手で調べという紐を持ち、右肩に乗せ、右手で下から叩くといった打楽器としては珍しい演奏の仕方です。
ポン、ポンと音色が響く楽器、鼓(つづみ)。歌舞伎や能などのお囃子で用いられる和楽器です。写真の鼓は小鼓(こづつみ)といい、左手で調べという紐を持ち、右肩に乗せ、右手で下から叩くといった打楽器としては珍しい演奏の仕方です。
他に小鼓と対で用いられる大鼓(おおづつみ/おおかわ)や、雅楽で用いる鞨鼓(かっこ)、三ノ鼓(さんのつづみ)などがあります。
古くは大陸からの伝来とされ、室町時代に流行した能と共に、鼓は形や音色などが発展し日本独自の楽器として歩んでいます。
木彫崑崙八仙(ころばせ)舞楽面
 こんろんはっせん、またははっせんとも呼ばれるこのお面。雅楽の一種である舞楽で用いる面で、鶴をかたどっており、羽を広げた甲を被り、尖ったくちばしに鈴を吊るし、四人で舞います。
こんろんはっせん、またははっせんとも呼ばれるこのお面。雅楽の一種である舞楽で用いる面で、鶴をかたどっており、羽を広げた甲を被り、尖ったくちばしに鈴を吊るし、四人で舞います。
崑崙山(こんろんさん)に住む仙人が鶴となり舞うという設定です。本来の鶴の姿より個性的な面相をしており、古来の独特な表現方法を感じることができます。
【雅楽】日本の古典音楽
中国を起源とし、宮廷や寺社の儀礼・祭礼における正統な音楽
木彫翁能面
 この柔らかな表情の老人は翁(おきな)といいます。能(能楽)で役者が用いる面であり、演目の一つとして扱われています。能は日本の伝統芸能であり、主にセリフがなく、役者の動きと伴奏(地謡と囃子)で表現します。その為、面はその表情で物語を観客に伝える役割も担っています。様々な表情の面がありますが、翁のように見ているこちらまでにこりとするような面もあり楽しめます。
この柔らかな表情の老人は翁(おきな)といいます。能(能楽)で役者が用いる面であり、演目の一つとして扱われています。能は日本の伝統芸能であり、主にセリフがなく、役者の動きと伴奏(地謡と囃子)で表現します。その為、面はその表情で物語を観客に伝える役割も担っています。様々な表情の面がありますが、翁のように見ているこちらまでにこりとするような面もあり楽しめます。
» 陶磁器の買取は京都の栄匠堂へご連絡下さい


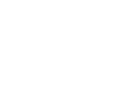
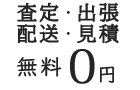
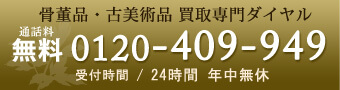


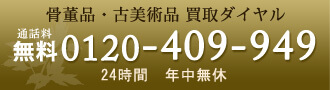

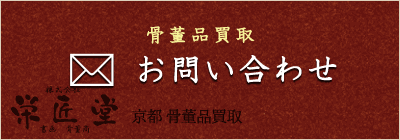





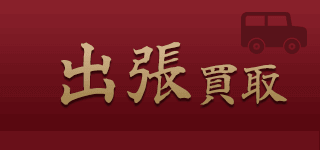
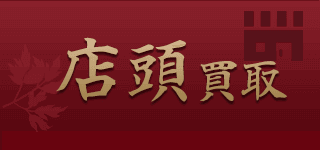
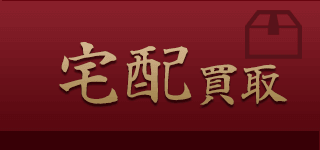
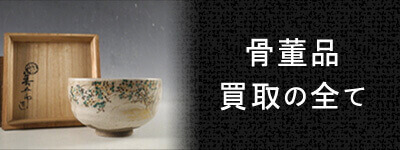
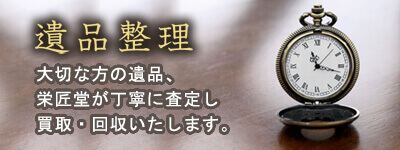
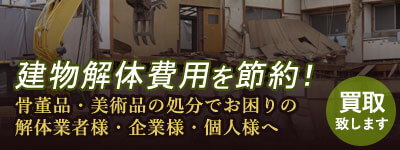

 茶道具・茶碗
茶道具・茶碗 煎茶道具
煎茶道具 華道具
華道具 書道具
書道具 陶磁器
陶磁器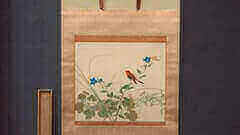 掛け軸・書画
掛け軸・書画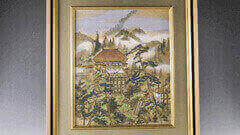 絵画 日本画・洋画
絵画 日本画・洋画 彫刻
彫刻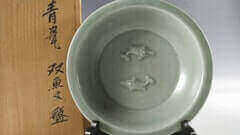 中国骨董
中国骨董 ガラス製品
ガラス製品 翡翠
翡翠 珊瑚
珊瑚 刀剣・日本刀
刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧
甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管
根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋
囲碁・将棋 香木
香木 西洋アンティーク
西洋アンティーク 金銀製品
金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品
錫・銅・ブロンズ製品 古書
古書 壷・甕
壷・甕 盆栽鉢・植木鉢
盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢
水盤・砂鉢 版画
版画