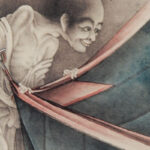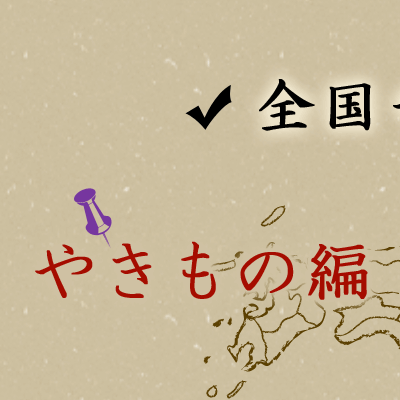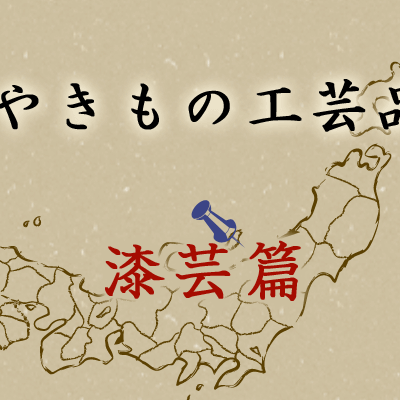一楽二萩三唐津
歴史の中で茶の湯と特に深い関係を築いてきた焼き物があります。茶の湯の中心で、茶人の間でも存在感を放っていた焼き物です。
茶道の世界では、古くから茶人の抹茶茶碗の好みの順位、もしくは格付けとして「一楽二萩三唐津(いちらく にはぎ さんからつ)」と言われてきました。これは、
1位: 楽焼 (京都)
2位: 萩焼 (山口県萩市)
3位: 唐津焼 (佐賀県唐津市)
を意味します。
No.1 楽焼 (京都)
 楽焼(らくやき)は、16世紀後半に瓦職人の長次郎がわび茶の世界を完成させた千利休の教えにより創案され、400年以上の伝統があります。聚楽第を建造する際に土中から掘り出された土「聚楽土」を使って焼いた「聚楽焼」が始まりとされています。
楽焼(らくやき)は、16世紀後半に瓦職人の長次郎がわび茶の世界を完成させた千利休の教えにより創案され、400年以上の伝統があります。聚楽第を建造する際に土中から掘り出された土「聚楽土」を使って焼いた「聚楽焼」が始まりとされています。
2代目・常慶の父・田中宗慶が豊臣秀吉より聚楽第の「樂」の印章を与えられ、家号にしたことから「楽焼」となった説が有名です。
楽家の楽焼を本窯、傍流(ぼうりゅう)の楽焼を脇窯と言います。
釉薬の色により黒(黒楽)と赤(赤楽)があります。
黒楽
 黒楽はほとんど図柄の無い黒一色で、格式が高い茶碗とされ、茶碗の重要な見所とされる高台(※1)も黒い釉薬で覆われ、胎土(素地)が見えません。
黒楽はほとんど図柄の無い黒一色で、格式が高い茶碗とされ、茶碗の重要な見所とされる高台(※1)も黒い釉薬で覆われ、胎土(素地)が見えません。
(※1 高台(こうだい):茶碗などの底につけられた円環状の台の部分)
黒楽は黒一色の「無」のみなので、禅の世界に通じるものがあり、「茶禅一味(ちゃぜんいちみ)」を具現化したものとされます。無作為そして単一であることで、それを使用する時々によってさまざまなことを考えさせられます。
また、この漆黒が抹茶の若草色の発色を引き立て、メリハリのあるコントラストが抹茶をより美味しそうに見せる効果もあります。
茶碗の世界は深く、さらに修行を続けなければ黒楽の本当の良さは分からないとする作家もいます。楽家は代々、これまでの保守的な伝統や個性の無い前衛的で斬新な作風の作品を生み出しています。
No.2 萩焼 (山口県萩市)
 萩焼は1604年に藩主・毛利輝元の命で、慶長の役の際、朝鮮人陶工、李勺光(山村家)・李敬(坂家)の兄弟が城下で御用窯を築いたのが始まりとされ、400年以上の歴史があります。
萩焼は1604年に藩主・毛利輝元の命で、慶長の役の際、朝鮮人陶工、李勺光(山村家)・李敬(坂家)の兄弟が城下で御用窯を築いたのが始まりとされ、400年以上の歴史があります。
初期のものは高麗茶碗(朝鮮半島)に似ており、手法も形状も同じものでした。現在でも土味、素地の景色、釉薬などが古い朝鮮茶碗に似ていると言われます。
萩焼の技術は1957年に文化財保護法に基づく「選択無形文化財(記録作成等の措置を講ずべき無形文化財)」に選ばれました。萩焼は山口県萩市で焼かれる陶器ですが、長門市・山口市にも一部、窯元がある。長門市で焼かれる萩焼は、深川萩(ふかわはぎ)とも呼ばれています。
萩焼はすり鉢のような井戸形の茶碗が多く、図柄もありません。釉薬が薄く掛かっているだけなので、ピンホール部分からお茶が染み込んで、次第に色が変わり、使い込んだ味わい深い茶碗になるおもしろさがあります。これを「萩の七化け」と言い、使い込むことが楽しみになります。
古くから茶人好みの器を焼いてきたことで知られる萩焼は、原料に用いられる陶土と混ぜる釉薬のバランスによって生じる「貫入」、使い込むことで生じる「七化け」が大きな特徴です。
貫入は器の表面の釉薬がひび割れたような状態になることで、七化けは長年使い込むことで貫入にお茶などが浸透し、器表面の色が変化して、枯れたような味わいを見せることです。模様は地味ですがファンが多く、萩市内には多数の窯元が存在しています。
No.3 唐津焼 (佐賀県唐津市)
 唐津焼(からつやき)は、近世初期から、佐賀県東部・長崎県北部で焼造された陶器の総称です。
唐津焼(からつやき)は、近世初期から、佐賀県東部・長崎県北部で焼造された陶器の総称です。
斉明天皇(655~661年)の時代に、神功皇后の三韓征伐の際に連れてきた高麗小次郎冠者が、日本で陶器を作り始めた頃が最初と考えられています。唐船が出入りする港の近くが唐津という地名になり、この地方の焼き物の名称にもなりました。
製品は茶陶以外にも日常雑器から茶器までさまざまな器種があり、作風や技法も多岐にわたります。九州地区では瀬戸物のことを唐津物と呼ぶほど広く親しまれてきた焼き物です。
絵模様のあるのを絵唐津と言い、シンプルでモノトーンの絵が多いようです。
» 栄匠堂では楽焼、萩焼、唐津焼の茶道具を高価買取しています


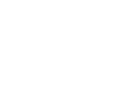
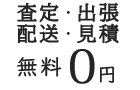





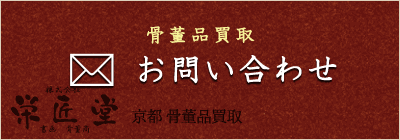












 茶道具・茶碗
茶道具・茶碗 煎茶道具
煎茶道具 華道具
華道具 書道具
書道具 陶磁器
陶磁器 掛け軸・書画
掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画
絵画 日本画・洋画 彫刻
彫刻 中国骨董
中国骨董 ガラス製品
ガラス製品 翡翠
翡翠 珊瑚
珊瑚 刀剣・日本刀
刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧
甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管
根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋
囲碁・将棋 香木
香木 西洋アンティーク
西洋アンティーク 金銀製品
金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品
錫・銅・ブロンズ製品 古書
古書 壷・甕
壷・甕 盆栽鉢・植木鉢
盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢
水盤・砂鉢 版画
版画