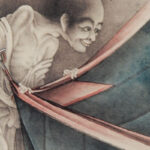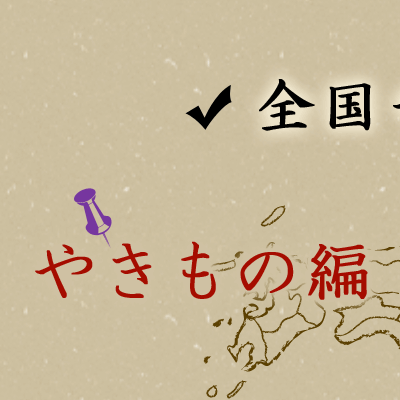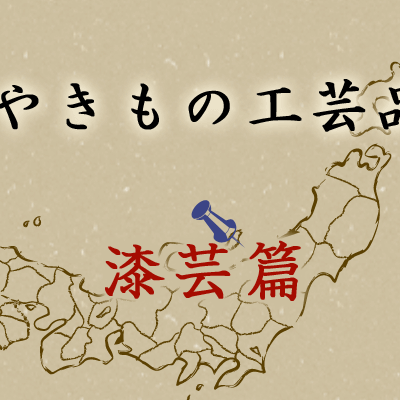猿投の歴史
 猿投山西南麓古窯址群(一般的に「猿投窯」と呼ばれています)は、愛知県尾張地方南部に形成された1,000基以上の古窯地帯で、瀬戸市、豊田市、名古屋市、刈谷市など20km四方の大変広い地域に分布しています。歴史も900年以上と古く、古代の須恵器窯から中世の山茶碗窯に至ります。
猿投山西南麓古窯址群(一般的に「猿投窯」と呼ばれています)は、愛知県尾張地方南部に形成された1,000基以上の古窯地帯で、瀬戸市、豊田市、名古屋市、刈谷市など20km四方の大変広い地域に分布しています。歴史も900年以上と古く、古代の須恵器窯から中世の山茶碗窯に至ります。
猿投窯の全盛期といわれているのは奈良~平安時代で長期にわたり、多様な器種の「灰釉陶器」が造られていました。大陸から輸入された陶磁や金属器を模倣した精巧なものが多く、寺院や貴族層の人々が利用していました。平安末期からは徐々に製品が粗悪になり、鎌倉時代には施釉の伝統も消失して山茶碗などの無釉の雑器が生産されるようになると、窯は次第に衰退して廃業していきました。
瀬戸投の歴史
瀬戸では900年以上も前から絶えず焼きものを生産し続けてきました。一部の地域では焼きものを「せともの」と呼ぶように、瀬戸は日本を代表する窯業地です。鎌倉初期に瀬戸陶祖の「加藤四郎座衛門景正(通称・藤四郎)」が、道元禅師に随行して宋に渡り、諸州各地をまわり歩いて陶業を学び、帰国後に瀬戸に窯を築いて、中国風の陶器を焼き始めたのが始まりとされています。鎌倉~室町時代において、瀬戸は日本唯一の「施釉陶器」の生産地で、この時代のものを古瀬戸と言います。主に宋や高麗の青磁、白磁を写した高級品が焼成されていました。
桃山~江戸前期には、当時新興であった有田磁器におされるなどして一時衰退しましたが、江戸後期の文化年間に「加藤民吉」が磁器製法を導入して染付磁器を中心とする瀬戸新製焼を興し、人気が復活しました。現在も食器、置物などの日用品から建築、工業用品まで、様々な場面で瀬戸の陶磁が焼造されています。
猿投の特色
 奈良時代末期~平安後期、猿投窯で一貫して生産された主な製品は、白瓷(しらし)とよばれていた灰釉の陶器です。また、平安中期までは各窯で共に須恵器が焼かれていました。平安中期~後期には、一部の地区で緑釉(800度以下の低火度で熔解する鉛を含有した釉)も焼成されていましたが、それ以外は、少数の雑器を除くほとんどの作品に灰釉がかけられています。
奈良時代末期~平安後期、猿投窯で一貫して生産された主な製品は、白瓷(しらし)とよばれていた灰釉の陶器です。また、平安中期までは各窯で共に須恵器が焼かれていました。平安中期~後期には、一部の地区で緑釉(800度以下の低火度で熔解する鉛を含有した釉)も焼成されていましたが、それ以外は、少数の雑器を除くほとんどの作品に灰釉がかけられています。
奈良時代の中頃に、猿投窯の須恵器に人工的に灰釉が施されるようになったとされています。この時期の人工的な灰釉の作品は、燃料の灰がふりかかって熔解した「自然釉」と区別しにくいものが多くなっています。比較的低火度で焼成される須恵器と異なり、灰釉の熔解温度は1,240度で高い火度を必要とします。奈良時代末期からは灰釉陶の生産が本格的になりました。高い火度を得るために須恵器の窯に様々な工夫がされています。また、灰釉陶と須恵器を同時に焼成する際には、焚口に近い所に灰釉陶を、奥には須恵器を窯詰めした跡が残っています。
猿投の灰釉
猿投の灰釉の原料は「植物灰」です。中世の古瀬戸の灰釉とは異なり、それぞれの作品が1種類の成分のみで使われるため、釉の層は大変薄く剥奪しやすくなっています。長く土中にあった出土品も釉が剥げ落ちてしまったものが多いです。釉色は淡緑色または黄緑色をしており、初期の施釉法は刷毛塗り、後に漬け掛けとなりました。
猿投の土
陶土は耐火度が高く、粒子の極めて細かい白色の良土が使用され、須恵器のものとは違っています。これらのことから、この時代には既に「水簸(すいひ)」が行われていた可能性があります。
(水簸:粉砕した鉱石を流水にさらして比重の小さい部分を洗い流し、底に沈んだ重い部分を取り出す方法。 砂金の分別採集によく用いられます。)
猿投陶の成形
猿投陶の成形は奈良時代末期から、ロクロ台の上に土塊をのせ水挽きで一気に挽き上げる「ロクロ造り」です。ロクロ技術は大変高度で、後世の人にも真似できないような精器が多数生産されています。厚さ数ミリの薄いもの、高さ・直径が30cmを超える大きなものなども自在に挽きこなしていた様子が伺えます。
猿投陶の成形
器種は古墳時代から生産されてきた須恵器の流れをくむものと、大陸の陶磁や仏具などを写したものがあります。須恵器後継には「長頸瓶」と「広口の短頸壺」があります。中国陶磁の写しには、唐三彩や越州窯の磁器の模倣が多く、仏具では肩にも注口のある「浄瓶」、楕円形の胴体と細長い首をもつ「水瓶」が多く生産されました。浄瓶、水瓶は、もとは金属製(佐波理:さはり)で、寺院で使用されていました。
猿投では多様な陶硯が生産され、円面硯、宝珠硯、風字硯の三種が代表的です。他にも小さな陶塔や仏像、馬などが作られていました。
古瀬戸の特色
古瀬戸の釉薬
 古瀬戸の釉薬は伝統的な「灰釉」と、鎌倉後期から使われるようになった「鉄釉」の2種類が基本です。平安時代の猿投の灰釉は灰単味ですが、古瀬戸の時代になると灰に長石が混合されるようになりました。長石に含有されている珪酸とアルカリと、灰に含まれるアルカリ分とが混ざり、焼成中に釉はガラス質になります。そのため熔解しやすく器体との密着も強固になります。
古瀬戸の釉薬は伝統的な「灰釉」と、鎌倉後期から使われるようになった「鉄釉」の2種類が基本です。平安時代の猿投の灰釉は灰単味ですが、古瀬戸の時代になると灰に長石が混合されるようになりました。長石に含有されている珪酸とアルカリと、灰に含まれるアルカリ分とが混ざり、焼成中に釉はガラス質になります。そのため熔解しやすく器体との密着も強固になります。
長石を含んだ灰釉は、灰と長石の比率によって性質が異なります。灰に対して長石が少ない場合、釉は不透明で流れやすくなり、長石の含有率がおおよそ70%を超えると釉は流れない性質を持つようになり、釉面は厚く平坦で透明度も高くなります。
(これに鉄分を入れると青磁や飴釉、天目軸となります。)
灰釉と長石
鎌倉時代の灰釉は長石が少ないため不安定で、焼成中にいくつも縞になって流れ落ちていました。流れ方も不規則的で、珪酸特融の結晶性により、火度が上がるにつれてさまざまなな方向へ流れだします。この時期のものは完器であってもほとんどが出土品です。長く土中にあったため、水に溶けやすいアルカリ分が流れ出て貫入が大きく、深くなり、釉の透明度も濁り、くすんだ色調をしています。
当時の長石はアルカリ分の多い風化した長石が使われ、焼成中に灰の成分と複雑な反応をして、この時代独特の釉流れと貫入を起こしています。精製された現在の原料では、当時のような釉の流れ方、貫入、光沢を模倣することは不可能とされています。弗化水素などで光沢を消すことはできますが、長い期間に徐々に変化してきたものとは違います。
古瀬戸の鉄釉
鎌倉期の後期から使われ始めた鉄釉は「飴釉」といわれるもので、透明性のある茶褐色をしており、濃淡が著しくムラがあります。薄くかけることで、器体に施された(当時全盛の)装飾文が映えるように活かされています。
室町時代には灰釉、飴釉ともに混合される長石の比率が高くなり、釉は厚く安定します。この時期には天目釉が現れ、中国建盞(けんさん:宋、元代に中国福建省の建窯でつくられた天目茶碗)の天目釉は、紺色がかった黒(蒼黒)ですが、古瀬戸の鉄釉は赤みを含み、潤いのあるのが特徴です(古瀬戸釉)。
古瀬戸の土
原料には土中の酸化鉄が自然に集まって板状に固まった「鬼板(おにいた)」が使用されまし。鎌倉時代の古瀬戸の成形は、手造りとロクロが併用され、小さなものはロクロ造り、壺や瓶は紐土の巻き上げや輪積みによって器体が造られ、表面のみがロクロで仕上げられています。猿投陶や須恵器が最初からロクロで挽き上げて造られることを考えると、技術的に後退したともいえますが、ロクロで引き上げた成形ではこの時期の壺や瓶のもつ肩の張りは造れないため、鎌倉期の古瀬戸の力強さは手造りによる器形ならではのものです。
室町時代には壺や瓶もロクロで挽き上げられ、器形は整った精巧なものとなり、肩の張りや力強さはなくなりました。鎌倉時代後期に全盛となった古瀬戸が誇る印花文や貼花文の装飾法は、室町期に釉薬が厚くなるにつれてほぼ消滅し、簡略なものが残りました。

大石訓義造 猿投窯 蹄脚硯

黄瀬戸 加藤作助 茶碗

井上良斎 造 瀬戸 水指

瀬戸 加藤繁十製 金彩色絵 龍双耳花入

清水六兵衛 黄瀬戸 瓢形

黄瀬戸 加藤舜陶 立鼓花入

二八代 加藤唐三郎 黄瀬戸 皿

初代 清水六兵衛 瀬戸釉 船形釣花入

瀬戸黒 平正窯 瑞兎図 茶碗

瀬戸 杉浦芳樹 柚子黒 茶碗


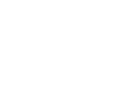
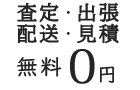





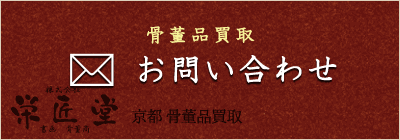












 茶道具・茶碗
茶道具・茶碗 煎茶道具
煎茶道具 華道具
華道具 書道具
書道具 陶磁器
陶磁器 掛け軸・書画
掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画
絵画 日本画・洋画 彫刻
彫刻 中国骨董
中国骨董 ガラス製品
ガラス製品 翡翠
翡翠 珊瑚
珊瑚 刀剣・日本刀
刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧
甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管
根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋
囲碁・将棋 香木
香木 西洋アンティーク
西洋アンティーク 金銀製品
金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品
錫・銅・ブロンズ製品 古書
古書 壷・甕
壷・甕 盆栽鉢・植木鉢
盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢
水盤・砂鉢 版画
版画