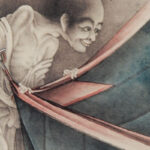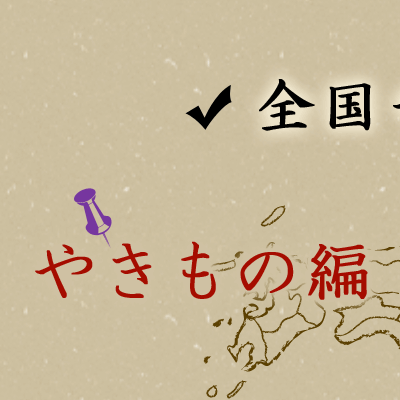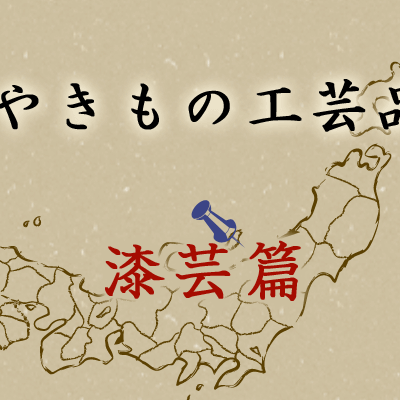色絵の誕生
 釉薬をかけて一度焼いた陶磁器に、色絵具で絵を描いて(絵付:えつけをして)、もう一度窯に入れて焼く「二度焼き」の技法で作られる陶器を色絵と呼びます。早くから多彩陶器はペルシャや中国の唐三彩などで製作されてきましたが、二度焼きによる色絵は12、14世紀頃にはじめて中国でつくられました。鉄分を含む灰色の素地に白化粧を施し、透明釉をかけて焼き、釉上に赤や緑の絵具で文様を描いて低火度で焼き付けていました。宋赤絵と呼ばれるものです。
釉薬をかけて一度焼いた陶磁器に、色絵具で絵を描いて(絵付:えつけをして)、もう一度窯に入れて焼く「二度焼き」の技法で作られる陶器を色絵と呼びます。早くから多彩陶器はペルシャや中国の唐三彩などで製作されてきましたが、二度焼きによる色絵は12、14世紀頃にはじめて中国でつくられました。鉄分を含む灰色の素地に白化粧を施し、透明釉をかけて焼き、釉上に赤や緑の絵具で文様を描いて低火度で焼き付けていました。宋赤絵と呼ばれるものです。
中国で色絵が豊富につくられるようになったのは明代のことです。景徳鎮では多様な色絵が作られ、成化の豆彩(とうさい)は気品と繊細を備えた作風で、遺品が少なく、17世紀以降の清代になってから人気が高まり、現在でも高い評価を得ています。また嘉靖、万暦期の五彩は濃厚で細かな様相特徴的です。
また、安南(ベトナム)と日本でも色絵磁器が作られ、日本では肥前有田地方で17世紀に色絵磁器が完成し、古伊万里、柿右衛門、鍋島などの様式が誕生しました。同じ頃、京都では色絵陶器もつくりはじめられています。幕末の京都では奥田頴川(おくだえいせん)によって色絵磁器も焼かれ、華やかな色絵文化が咲きました。
中国の色絵の移り変わり
「宋赤絵」と呼ばれる色絵は、生成り色に近い白い釉上に、赤・緑・黄色でのびやかに草花やうさぎ、魚などが描かれています。宋赤絵は磁州窯系の窯で焼かれたことが分かってきていますが、この赤絵の技法が景徳鎮窯に伝わった経緯や、どのように明代で盛んになっったのかなどは明らかではありません。
明代初期には赤一色を用いた作品が多かったのですが、それは当時盛んであった釉裏紅(ゆうりこう)に似た効果を簡単に得るための方法であったとも考えられています。色釉の数が増えたのは成化期(1465~1488年)のことで、主に淡い緑青色が用いられ、そこに黄、赤、紫などが加えられて、優雅な色調となっています。赤はごく僅かに点じられるだけの成化の色絵は「豆彩」と呼ばれ、明代第一の色絵として珍重されています。
成化豆彩に続いて景徳鎮の官窯では、青花文様を下地にしてこれに上絵を加える「青花五彩」の装飾法が発達しました。
嘉靖期には、色絵磁器は多色を用いた多様な作風を示すものになります。官窯で色絵磁器が主体になっていくのもこの頃からで、民窯による色絵磁器の盛行に影響されたと考えられています。
15~16世紀にかけて景徳鎮の民窯で焼かれていた無銘の色絵磁器が残っていますが、染付を伴わず、上絵だけのものが多いのが特徴です。
日本では古赤絵と呼び、多くは、赤で輪郭をとってその中を緑や黄で埋めた華麗な色調です。花鳥文、魚藻文、物語図などさまざまな素材が描いてありますが、どれも自由でのびやかに表現されています。一般的には銘款が無く、民窯でつくられたと考えられています。
景徳鎮の民窯で作られた五彩磁に金彩を施した「金襴手(きんらんで)」と呼ばれるものがあります。古赤絵との作風の違いは意匠であると言えます。金襴手には、古赤絵によく用いられている具象文が少なく、細密な技巧をこらした幾何学文が多用され、鮮やかな金彩と大胆な装飾性が特徴的な作品です。
金彩との違いは、器表を緑・赤・三彩などで塗り埋め、その上に金箔を焼きつけて文様を表すことが多く、碗、鉢のほかに仙盞瓶型水注や瓢型瓶なども見られます。
万暦期の官窯の製品には、濃密な青花と五彩により、器表に文様を密に描き込まれたものがたくさんあります。主に赤と緑が用いられ、わずかに黄色が点じられて、万暦赤絵では青花の濃厚な藍色も上絵具と同じような効果をもたらせています。各種の合子(ごうす:身と蓋とからなる小型の容器)や、古銅器を写した器形のものなどが作られ、大型のものもしばしば見られます。
明末期~清初期の景徳鎮で、官窯はその生産を中止しましたが、代わって民窯が天啓赤絵、色絵祥瑞、南京赤絵などの五彩磁を生産しました。特に南京赤絵と呼ばれる繊細な色絵は次第に洗練され、清朝康熙官窯の五彩へと発展していったとされています。
清代の官窯色絵磁器は、その精緻な白磁と豊富な色料、そして粉彩あるいは洋彩といわれている新しい色絵技法が用いられました。粉彩は雍正期(1723~1736年)頃に始められたとされていますが、現在では、康熙(1662~1722年)末頃にはすでに行われていたと推測されています。
粉彩とは白磁の釉肌に、石英砂の類に鉛粉を混ぜた琺瑯(ほうろう)料を塗り、これを下地にして彩色した色絵です。光沢のある釉肌と違い、吸着性のある琺瑯質の下地の上に描くため、微妙な濃淡や中間色を得られ、繊細華麗で上質の上絵磁器とされました。
中でも皇帝の座右に置くために作られた古月軒(こげつけん)といわれる粉彩磁は、白玉のような釉肌と絵付が大変美しい作品です。北京の宮中如意館の画院の名画工達の筆(て)になるものといわれ、絵にそえて題句が書かれ、印章が押されています。古月軒はその精緻かつ優美な姿が人々を魅了し、清代を代表する最高の色絵磁器と称されています。
色絵の贋作
色絵の贋作は、白磁や染付のものに後から上絵を付けて焼くという、ほとんどが「後絵付」のものです。タイ・バンコクなどの古美術品店では、色蠟で絵を描いただけの贋物が見られることもあり、白呉須のキズ物に色蠟で絵付をしたものなど、よく出来ているために騙されて購入する人も少なくありません。
赤絵などの色絵の贋作の場合も先述の後絵付のものが多く出回っています。本焼きと上絵付とが同時代に同じ窯場でされたものであれば問題はありませんが、天啓時代の染付に、後世になってから後絵付をして天啓赤絵とするなど、半真半贋といえるものもあります。天啓染付の真もこのような上描きによって贋作とされてしまうのは大変残念です。
これらは、絵柄をじっくりと見て上絵の部分を消し去った絵柄をイメージしてみると、染付の部分だけで絵柄としてまとまっています。また、長年使用したものに後絵付すると、上絵の下層の器肌には使い込まれた細かな傷が見られますが、上絵の部分はきれいなので、見分けることができます。
ただし、磁器は土ものに比べて古色がつきにくく、器肌も変化しにくいため、古いものでも現代のものと見た目はあまり変わりません。そこに昔と同じ彩料を用いて同じ後絵付がされていれば、見分けるのは大変難しくなります。
色絵の真贋がむずかしいと言われるのはこういった背景があるからです。
中国赤絵の輸出
インドネシアの首都・ジャカルタの国立博物館には、南ボルネオのマルタプラ遺存のものとされている、呉須赤絵の帆船図大皿が収蔵されています。スマトラやジャカルタには中国で製作された赤絵の遺品が多く、トルコ・イスタンブールのトプカピ宮殿にも優品が遺されています。
17世紀にオランダ東印度会社が、福健省の墇州(しょうしゅう:中国にかつて存在した州)からバタビア(現ジャカルタ)を中継地として、イランをはじめ、ヨーロッパ各地に中国の赤絵を輸送していました。ヨーロッパ向けの主な輸出品は、官窯の精巧な上手ものだったのに比べ、日本に多く輸出されたのは民窯で焼かれた古赤絵や呉須赤絵でした。日本では、やや くだけたこれらの赤絵の方が人気がありました。
彩色の成分
色絵の彩料はすべて鉱物で、これらは酸化炎(開放して空気を多くとり入れて焼成する)と還元炎(窯を密閉して焼く)によって、それぞれの鉱物特有の発色を引き出します。
鉄は酸化炎ならば茶褐色、還元炎ならば青緑、
銅は酸化炎ならば緑~青、還元炎ならば赤色(辰砂)
といった風に発色させます。
・赤:第三酸化鉄
・黄:ルチール
・黄緑:銅とクローム
・青緑:銅
・青:コバルト(コバルトの量により薄青、青、群青などと色が変わります)
・紫:二酸化マンガンコバルト
・ピンク:二酸化マンガン
・茶:第一酸化鉄
・濃い茶(濃い褐色):第一酸化鉄とクローム
・黒:第一酸化鉄/マンガン/コバルト
・金:純金

古鍋島 色絵飾皿

色絵 急須

色絵 花鳥飾皿

色絵 四弁花紋飾皿

フランス 皇室セーブル窯 色絵

古伊万里 色絵

古伊万里 色絵 姫皿

金彩 色絵 飾皿

金彩色絵 急須

マイセン 色絵 鶏

古伊万里 金彩 色絵

中国 色絵

金彩色絵

中国 色絵 龍

中国 色絵

中国 金彩色絵


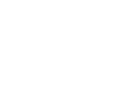
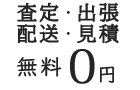





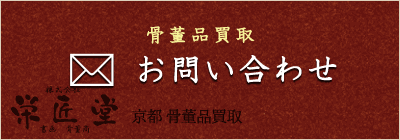


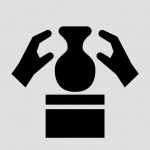
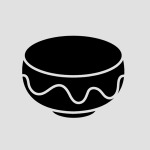








 茶道具・茶碗
茶道具・茶碗 煎茶道具
煎茶道具 華道具
華道具 書道具
書道具 陶磁器
陶磁器 掛け軸・書画
掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画
絵画 日本画・洋画 彫刻
彫刻 中国骨董
中国骨董 ガラス製品
ガラス製品 翡翠
翡翠 珊瑚
珊瑚 刀剣・日本刀
刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧
甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管
根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋
囲碁・将棋 香木
香木 西洋アンティーク
西洋アンティーク 金銀製品
金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品
錫・銅・ブロンズ製品 古書
古書 壷・甕
壷・甕 盆栽鉢・植木鉢
盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢
水盤・砂鉢 版画
版画