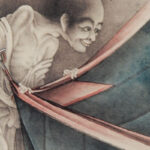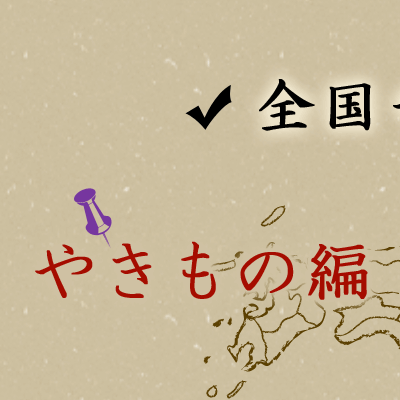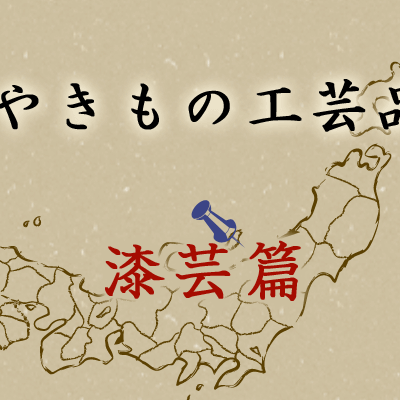やきものを鑑定できるようになるには、一定の知識を持ち、出来るだけ多くの作品を見ることが重要となります。
やきものの一般的な見分け方について紹介します。
土(つち)
古陶器を詳しく調べる際には、必ず裏返して底の「高台(こうだい)」を見ます。その理由のひとつは、露出している胎土(たいど)を確認するためです。産地が違っても、釉やカタチは似たものが多いですが、胎土は窯場が違えば異なる特徴を持っているため、高台を見ることは産地を特定する有効な情報となります。
骨董品は古い時代に焼かれたものです。現在とは違い、昔は土のある所に窯場が築かれ、やきものの土は地元で採れるもののみを使い、他所から運ばれてくることはありませんでした。そのため、土を見れば産地を特定するヒントのひとつとなります。
例)特徴を捉えるのが難しい黒釉(こくゆう)の小壺の産地
- ・灰白色の均質の土 → 中国の磁州窯
- ・キツネ色に焼締り黒色の繊細な点があらわれている土 → タイのサワンカローク窯
- ・赤みが強く艶がない土 → 薩摩の苗代川窯
- ・褐色系で砂っぽく見えながら粘性がある土 → 唐津
- ・淡黄味を帯びた白のやわらかい土 → 美濃
土の特徴を知るには同じタイプの作品を並べてみると分かりやすいです。
例)無釉で茶褐色、器形もよく似た日本の中世の壺です。
- ・常滑 → 粒子が粗く砂のような印象です。淡褐色から褐色で艶は少ないです。
- ・越前 → 常滑と酷似しますがやや艶があります。
- ・渥美 → 常滑よりきめは細かいですが、小石が混入していることがあります。灰褐色をしています。
- ・信楽 → 白い長石の粒が無数にあり、明るい発色が多く、華やかな緋色(あかいろ)もあります。室町時代のものまでは艶がありません。
- ・丹波 → 備前に次いできめ細かく、明るい褐色が多く、艶があります。
- ・備前 → 最もきめ細かくねっとりとした土で作られており、艶が強いです。基本は暗褐色ですが窯変で明るい緋色も出ます。
大まかに特徴を書きましたが、実際には似た土も多く、また同じ土でも焼成方法によって外観も変わり、粒子の大きさや土に含まれている鉄分や微細な混入物が混ざって、やきものの胎土はさまざまに変化します。これらをすべて覚えるとなると難しいと思われますが、代表的な地域や古窯の胎土の特徴を覚えておくと、方向性に見当がつくようになります。胎土によって陶磁器の形や様相、釉薬の発色も微妙に影響を受けるため、土を見極めてこそ、古陶器の産地を確定する手掛かりとなるのです。
一部を除いたほとんどの地域で、昔使われた陶土や磁土はまだその産地にあり、今も使用されていますので、土を見るだけでつくられた「時代」を確定することはできません。
造形(ぞうけい)
壺の外観
時代の判定には造形技術の特徴、手法などを見分けることになります。
例えば壺の場合、同じように見えるものでも「ひもづくりで巻き上げていく技法」「轆轤(ろくろ)で挽き上げる方法」「型で抜く方法」があり、信楽や備前は中世まではひも作り、近代以降はろくろ挽きなど、窯や時代によって造形方法が違います。
また、同じ轆轤挽きでも、「壺の上下を別々にろくろで挽いて後で胴央を接着する胴継ぎの方法」や「轆轤で上まで引き上げる一本挽き」などがあります。
中国では明代の磁器は大壺から小壺まで胴継ぎでしたが、清代になるとほとんどが一本挽きでつくられています。
これらの違いは壺の中を見て判断できます。
高台
高台の場合、高台の輪を後から器本体に付ける「付け高台」と、轆轤で底部を厚く残し、ヘラで高台を掘り出す「掘り出し高台」があります。鎌倉期の常滑や瀬戸の山茶碗は付け高台、室町から後は掘り出し高台となりました。同じ桃山期の茶碗でも、美濃は付け高台が多く、唐津は掘り出しで作られています。
造形の方法
造形の方法は時代や窯により、それぞれ一定の方法でつくられており、例外はほとんどありません。
胎土は千差万別でしたが、造形方法の種類は少なく、全く違う時代や窯でも共通点があります。胴繋ぎは中国明代、朝鮮半島の李朝、日本では中世古窯の大壺などで見られ、型抜きは明代末の交趾(こうち)、江戸後期の長崎平戸焼など広く見られます。
時代特有の造形方法が見られないときは、作品自体を疑ってもよいほど、造形は判定の基準として分かりやすいものでもあります。方法は限られており、見分ける技能の習得も比較的簡単なため、基本的な造形方法は覚えることが可能です。
様式(ようしき)
古陶磁の形態や装飾なども、各時代や産地特有のものであるため、判定のポイントとなります。壺、皿、鉢などの形態は種類が少なく、似たものが見つかることも多いですが、厳密に調べれば産地や時代を超えて同じものはほとんどありません。
装飾、とりわけ絵付けなどの文様は、形態や造形手法に比べて多くの種類があり、古陶器の時代や産地の判別に有効です。
例えば明代の花文、朝鮮半島の三島の魚文、初期伊万里の松の描き方など、ほとんどの文様はその時代やその窯に特有の描法で描かれているからです。陶磁器の絵付けに多く登場する龍や唐草文なども、時代や産地によって少しずつ違っており、陶磁器の小さな破片に描かれた唐草文からも、どの時代のものかなどが分かることがあります。
これらの文様の全く同じものが後代も繰り返されることはなく、一時期同じような文様のものがどんなに多く焼かれていても、それはその時だけのものでと言えます。
例外と言えるのは「倣造品(ほうぞうひん)」「写し(うつし)」のものです。清朝時代に明代の古陶磁に倣った(ならった)もの、仁清や乾山を模して後代つくられたものなどで、これらは古陶磁の歴史においては大変少ない事例です。
無限に種類があるように見える文様も、描法を体系的に整理すると、各時代や産地を示すことができます。
古色(こしょく)
古色は「古びた感じ」のことで、新陶にはない独特の風格を見せる経年変化のことです。贋作が出回る際にも、この「古色」がほどこされているため、古色の見分け方も真贋判定のポイントとなります。
古陶器の経年変化のひとつは、人から人へ伝えられた「伝世品」に見られます。使用による擦れや、キズ、シミなどの汚れが付いています。もうひとつは土中や水中に埋没した発掘品に特有の「化学的変化」によるもので、「カセ」と呼ぶ胎土や釉薬の風化、釉薬の空洞化による乱反射(銀化)などがあります。
また、永年使用していた器が後世に埋没したものや、発掘した後永く使用したものなど、複合的に経年変化したものもあります。
一般に磁器は陶器に比べて汚れにくく科学的にも侵されにくい特徴があり、あまり変化しません。そんな磁器でも、焼の甘いものは貫入(かんにゅう:釉のひび)に汚れが入って茶色になっていたり、染付の色がうすれて粉が吹いたようなものもあります。
同じ時代につくられたものでも、使用の頻度や使われ方、土中の化学成分などによって古色のつきかたが異なり、古色からは年代を正確に推測することはできません。また、基本的に古陶器には何らかの古色が付いていますが、未使用のまま地上で建物の中で大切に保存されたものには、古色が全くついていないものもあります。
贋作や新作には、古さを装うためにこれらの古色をわざとつけているものが多く見られます。漆を薄く塗って茶渋が付いているように見せた茶碗や、紅茶などに漬けたり、煮たりして汚したもの、器面にサンドペーパーで擦り傷をつけたもの、フッ化水素などの薬品で釉薬を浸し、発掘品のように見せたものなど、その手法はさまざまです。
それでも注意深く見ると、自然な古色とは違うことが分かります。自然な古色と人工的な古色を見分けることは大変重要ですが、それ以上に、古陶器としての本体を見極めることが判定の目を持つという意味では重要となってきます。
実際、多くのケースで古く見えるものの方に贋作が多く、真作は大切に保管されていたためか、新しく見えることがあります。


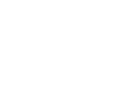
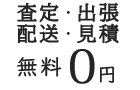





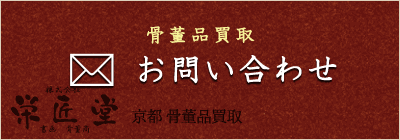










 茶道具・茶碗
茶道具・茶碗 煎茶道具
煎茶道具 華道具
華道具 書道具
書道具 陶磁器
陶磁器 掛け軸・書画
掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画
絵画 日本画・洋画 彫刻
彫刻 中国骨董
中国骨董 ガラス製品
ガラス製品 翡翠
翡翠 珊瑚
珊瑚 刀剣・日本刀
刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧
甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管
根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋
囲碁・将棋 香木
香木 西洋アンティーク
西洋アンティーク 金銀製品
金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品
錫・銅・ブロンズ製品 古書
古書 壷・甕
壷・甕 盆栽鉢・植木鉢
盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢
水盤・砂鉢 版画
版画