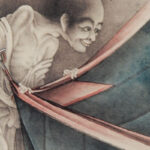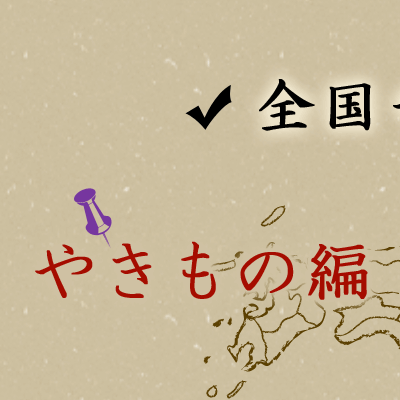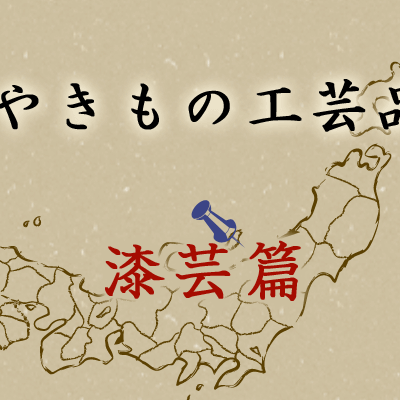墨(すみ)

 骨董品専門店 栄匠堂では
骨董品専門店 栄匠堂では
油煙墨、松煙墨(青墨)、唐墨、かな用墨、茶墨、漆墨、朱墨、金・銀・特殊墨、拓本用墨、古墨など
墨運堂、古梅園、日本製墨、呉竹や、中国の徽歙曹素功精の鉄斎翁書画寶墨、大好山水など、様々な墨を買取致します。
墨の種類
墨には植物油の煤(すす)からつくられる「油煙墨(ゆえんぼく)」と、松の木のヤニの出ている部分を燃やした煤でつくられる「松煙墨(しょうえんぼく)」などがあります。墨の歴史は松煙墨から始まりましたが、現在では主に油煙墨が使用されています。
松煙墨(しょうえんぼく)
松から煤を採った墨を「松煙墨」と言い、大小様々な大きさの粒子があるのが特徴で、色は「油煙墨」に比べ複雑です。「松煙墨」は年月が経つにつれて墨の色が変わって青みがますます強くなり、これが「青墨」と呼ばれる高級墨になります。
油煙墨(ゆえんぼく)
日本が作ったとされる油煙墨は、不純混合物がほとんど無く、墨色の変化も少ない特徴があります。油煙の炭素末粒子は松煙の炭素末粒子に比べて大変小さく均一になるため繊細な墨がつくれます。
油煙の炭素末となる原料には「菜種油」「胡麻油」「桐油」「椿油」があり、中でも「菜種油」が多く使用されています。
「濃墨」の場合は「艶(つや)と深みのある漆黒で奥行きのある黒色」を良質としています。
「淡墨」では、相対的に薄茶に紫味や青味を含んだ黒色を放ち、きめ細やかなにじみによる「立体感を得られるもの」を良質としています。
良質の油煙墨になる程、硯当たりが滑らかで磨り口の光沢が強くなります。
品質の劣る物は、濃墨の場合でも黒色が浅く、赤茶けたものや白茶けたものに仕上がっています。淡墨では、きめの粗い立体感のないものが劣品とされます。
品質の判断には豊富な経験が必要となり、墨の色は紙の質にも左右されるため、実際に試すのであれば同じ紙の上で比較しなければ正確な判別は難しいでしょう。
改良煤煙墨 洋煙墨(ようえんぼく)
改良煤煙墨は一般的には洋煙墨と呼ばれ、鉱物油やカーボンブラックなどを原料としています。松煙墨や油煙墨に劣ると言われ、墨本来が持つ「七色に光る」魅力が無いところが残念ですが、実用墨として多く使用されており、松煙墨や油煙墨より「早く黒くなる」のが特徴です。
最近では墨液が主流になってきていますが、墨液を使用するよりも洋煙墨を使用する方が、筆や硯の道具を長持ちさせます。

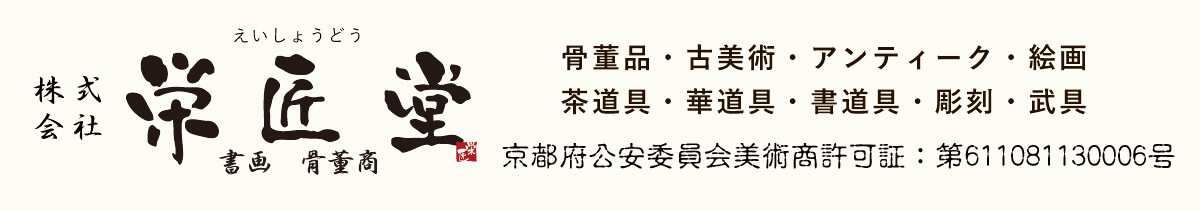


墨の特徴に大きくかかわる膠(にかわ)
 膠(にかわ)には墨を製造する際に、炭素末を接着させ、墨のカタチに固定する役割があります。そして、墨を硯で磨るときに、「光沢を持った墨色を出す」という重要な役割もあります。
膠(にかわ)には墨を製造する際に、炭素末を接着させ、墨のカタチに固定する役割があります。そして、墨を硯で磨るときに、「光沢を持った墨色を出す」という重要な役割もあります。
墨に使用される膠は、粘着力が強く透明でゼリー強度の強いものが良質とされますが、ゼリー強度が強すぎると、墨が硬くなり過ぎて墨おりが悪くなってしまうため、ほどよい調整が必要です。
膠が煙煤(えんばい)を包み込んで、水に溶けることを可能にし、液体の墨となります。
筆が紙に接地する摩擦の感覚は、この膠の感触と言えます。
実はここに勘違いがあり、「濃い墨はネバネバしている」「とろっとしている感覚」と表現されますが、墨の濃度と粘度(ネバネバした感覚)は別のものです。
濃度は墨液の全体量に対する炭素粒子の量の割合により変わり、粘度は墨液の全体量に対する膠の量の割合に影響されます。
墨の香料
膠(にかわ)は動物から取り出されるため強い異臭を放ちます。臭いを消すための香料を入れます。
香料は膠の悪臭を消してくれる働きがあり、墨には「天然香料」と「人造香料」があります。
天然香料は植物性香料と動物性香料とがあり、植物性香料では 「梅花香」、動物性香料では 「麝香(じゃこう)」が使用されます。
人造香料には 「ムクス・アンヅレット」「キシロール」などがあり、混合香料の原料となっています。
香料を混ぜるのは、その他にも墨の香によって、磨り手の精神を統一させる役割もあり落ち着いて書き物が出来る環境を作る、という大切な役割も担っています。
朱墨(しゅぼく・しゅずみ)
古くは朱は丹と呼ばれていました。当時の平城京の建物や寺社の柱などには防腐の役割りを果たす朱が塗られ、万葉集でも詠われた色彩の見事さからも、大変な貴重品として扱われてきました。室町末期に九州・博多へと伝来した朱は、貴重品として一般市民の朱採掘や売買、製造を禁止していました。
1609年に朱の製造や売買が認められるようになり、朱の製造が行なわれるようになったとされています。
明治時代には一般的に使用を許され、朱墨の訂正や印判が認められました。
高級な朱墨は水銀を加工して朱色を出し、年月の経過にも色が劣化しない特徴を持っています。
一方、安価な朱墨には顔料が使用され、年月の経過により色が劣化します。
朱墨に水銀が入っているか、密度が高いものかなどの状態を見て、朱墨の質を確かめます。


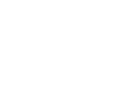
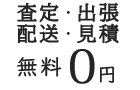





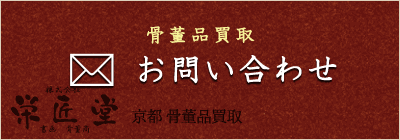







 茶道具・茶碗
茶道具・茶碗 煎茶道具
煎茶道具 華道具
華道具 書道具
書道具 陶磁器
陶磁器 掛け軸・書画
掛け軸・書画 絵画 日本画・洋画
絵画 日本画・洋画 彫刻
彫刻 中国骨董
中国骨董 ガラス製品
ガラス製品 翡翠
翡翠 珊瑚
珊瑚 刀剣・日本刀
刀剣・日本刀 甲冑 兜 鎧
甲冑 兜 鎧 根付・煙草入・煙管
根付・煙草入・煙管 囲碁・将棋
囲碁・将棋 香木
香木 西洋アンティーク
西洋アンティーク 金銀製品
金銀製品 錫・銅・ブロンズ製品
錫・銅・ブロンズ製品 古書
古書 壷・甕
壷・甕 盆栽鉢・植木鉢
盆栽鉢・植木鉢 水盤・砂鉢
水盤・砂鉢 版画
版画